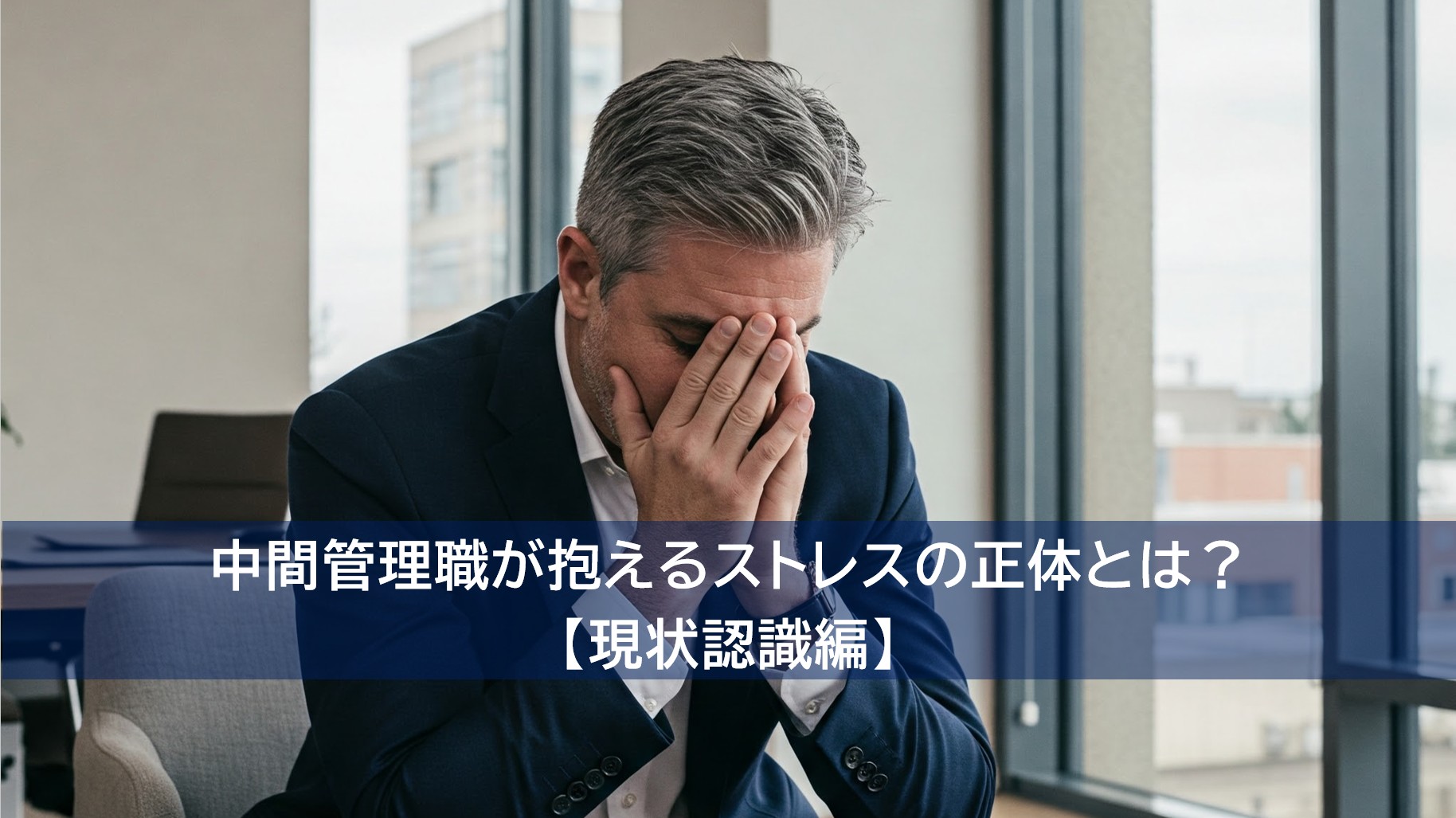本記事は、部下との構造的関係性とマネジメントについて、中間管理職と認識しておくべきことを記載します。従いまして、特にマネジメントの手法を示す訳ではありません。目的は、一緒に、世の中の中間管理職の現状を認識することで、少しでも、ストレス軽減にお役立て頂くことです。
さて早速ですが、この記事の読者の方の中には、実際に中間管理職の方が多いと思います。その方は、次のように感じているのではないでしょうか?
「上からの指示と下からの不満の板挟みで、正直しんどい…」
中間管理職という立場は、組織の中でもっともストレスが溜まりやすいポジションと言われています。現場と経営の間に立ち、両方の視点を理解しながらチームを牽引しなければならない。しかも、それをやり遂げるには高いスキルと精神力が求められるのです。
一般的には、中間管理職が抱える主なストレスには下記があると言われています。
❶上司からのプレッシャー
経営層からの指示は時に現場の実情を無視したものになることも。数字の達成を迫られたり、短期間での変革を求められたりと、プレッシャーは常に付きまといます。
❷部下からの不満や期待
一方で、部下からは「もっと分かってほしい」「上司は現場のことを知らない」といった声が上がります。信頼を得たい一心で努力しても、なかなか伝わらない苦しさもあります。
❸業務過多とマルチタスク
会議、資料作成、マネジメント、実務…。1日のスケジュールは分刻みで、常に何かに追われている感覚。何を優先すべきか悩む日々に疲弊してしまうことも少なくありません。
❹評価の板挟み
部下を守りたい気持ちと、上層部に結果を報告しなければならない立場。成果と人間関係、どちらを取るべきかというジレンマに頭を悩ませる場面も多いでしょう。
❺孤独感
同じ悩みを共有できる相手がいない。愚痴を言える場がない。そんな「孤独な戦い」が心の負担を大きくしています。
ここまでは、よく言われる一般的なストレスの項目になりますが、もう少し、実務よりの話をすると、下記のようなことを感じていませんか?
「私のチームは、年齢や性別、学歴が多様であり、一元的な管理が難しい」
私もこの意見には共感します。そして、このことが中間管理職のマネジメントを難しくしている大きな要因の1つなのです。
組織において、常に対等な立場の人間と仕事をすることはほぼありません。通常は上司や先輩がいて、部下や後輩がいるという階層構造の中で業務を遂行します。これは、若手社員から部長クラスのベテラン社員まで共通することです。
しかし、この階層の中で大きく異なるのが、部下や後輩の多様性です。
例えば、部長の部下は主に課長クラスですが、課長はこれまでにさまざまな経験を積み、適切な能力を備えている人材が登用されます。そのため、部長のマネジメントは一定のルールを示し、方針を決めれば大きな問題なく進めることが可能です。これにより、部長は社外との交渉や企業戦略の策定などに時間を割くことができます。
しかし、課長は事情が異なります。課長の部下は、概ね、年齢や性別、学歴が多様であり、単一のルールに従わせることが難しい場面が多々あります。そのため、個々のメンバーに合わせたマネジメントを実施する必要があることが、難しい要因なのです。
企業の採用において、学生時代に力をいれたこと通称「ガクチカ」や、クラスや部活、サークルでのリーダー経験が重視される理由もここに関連しています。
採用において、なぜそれらが重要視されるのでしょうか?それは、このような経験の有無によって、チームにおけるマインド(組織のモラールと呼ばれる)が大きく異なるからです。
例えば、リーダー未経験の人は、
- 個人的な意見を主張するが、チーム全体の目標や方向性を考慮しない
- 最終的な出口(ゴール)のイメージを持てず、建設的な議論ができない
- あるいは、そもそも議論に参加せず、ただ指示を待つだけになってしまう
こうした傾向が見られることがあります。その結果、チーム内の意思決定においてスムーズな進行ができず、無駄な時間を消費してしまうのです。
一方で、リーダー経験者は、出口(ゴール)を意識した思考ができるため、チーム全体を建設的な議論へと導く能力を持っています。
- 独自の意見を持ちつつも、チーム全体の方向性を考慮できる
- 課題を解決し、目標達成に向けた具体的なアクションを取ることができる
- 無駄な時間を削減し、議論の着地点を明確にできる
この違いが、リーダー経験のある人材が組織において求められる理由なのです。ただし、破壊的なイノベーションを起こしたい場合には、このチーム力が逆に不利に働くこともあると思います。
ここまでに書いた、中間管理職とメンバーやスタッフとの構造を考えると、採用活動の段階から人事部をはじめとした組織が、戦略的に人材を採用する必要があるということです。それは、将来的にリーダーになる人材、そのリーダーをフォローする人材というように、全体最適を目指すことが重要になります。
とはいえ、狙った人材が必ず獲得できたり、採用した後に実は・・・的なこともあるので、そう簡単でないことも周知の事実としてあります。
さて、ここまで中間管理職のマネジメントが難しい要因について書きましたが、いかがでしたでしょうか?
そして、この現状を鑑みると、自分自身がマネジメントに苦戦するのも無理がないと思えるのではないでしょうか?
なので、わたしの結論は、割り切ってマネジメントを行いましょう!ということです。そして、少しでもストレスを軽減しながら、一緒にマネジメントを楽しみましょう!